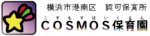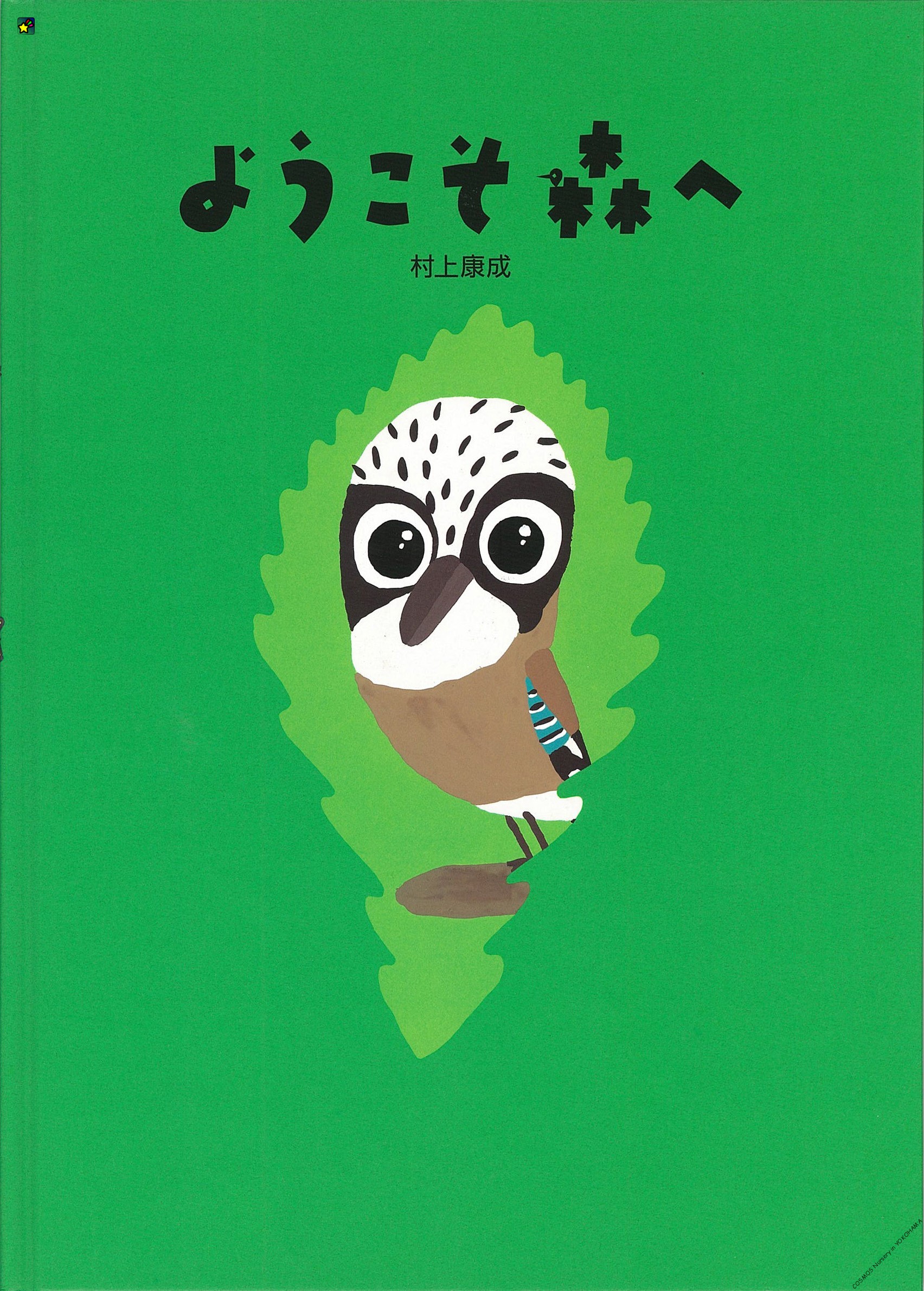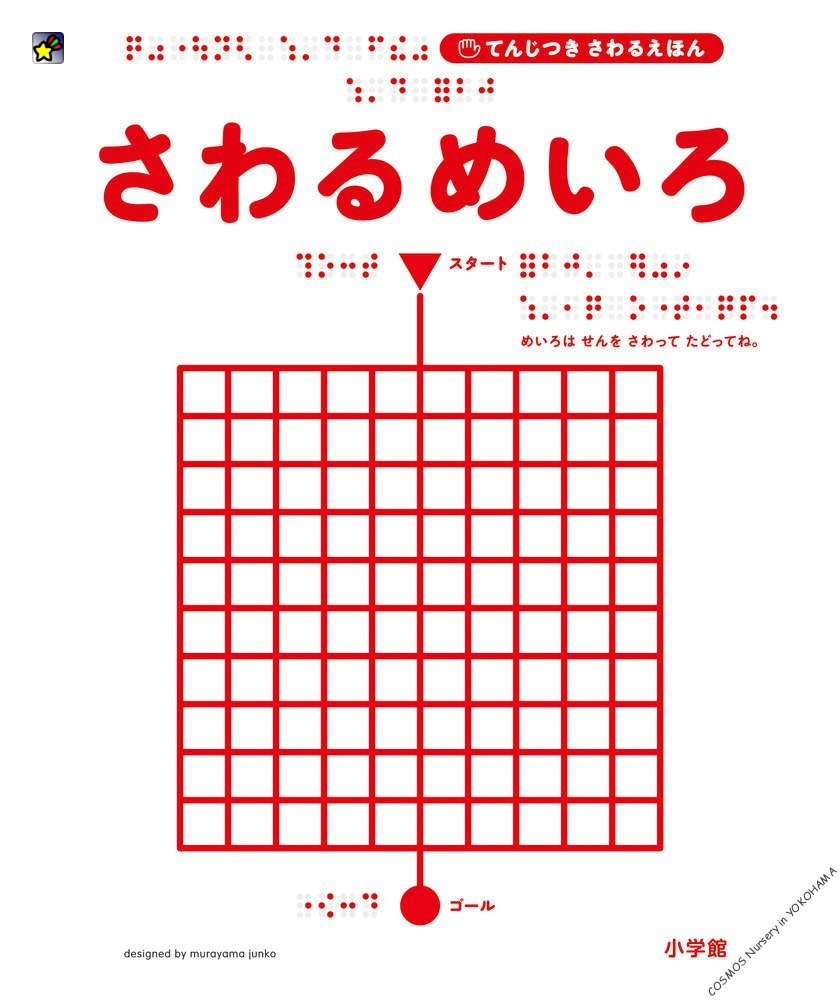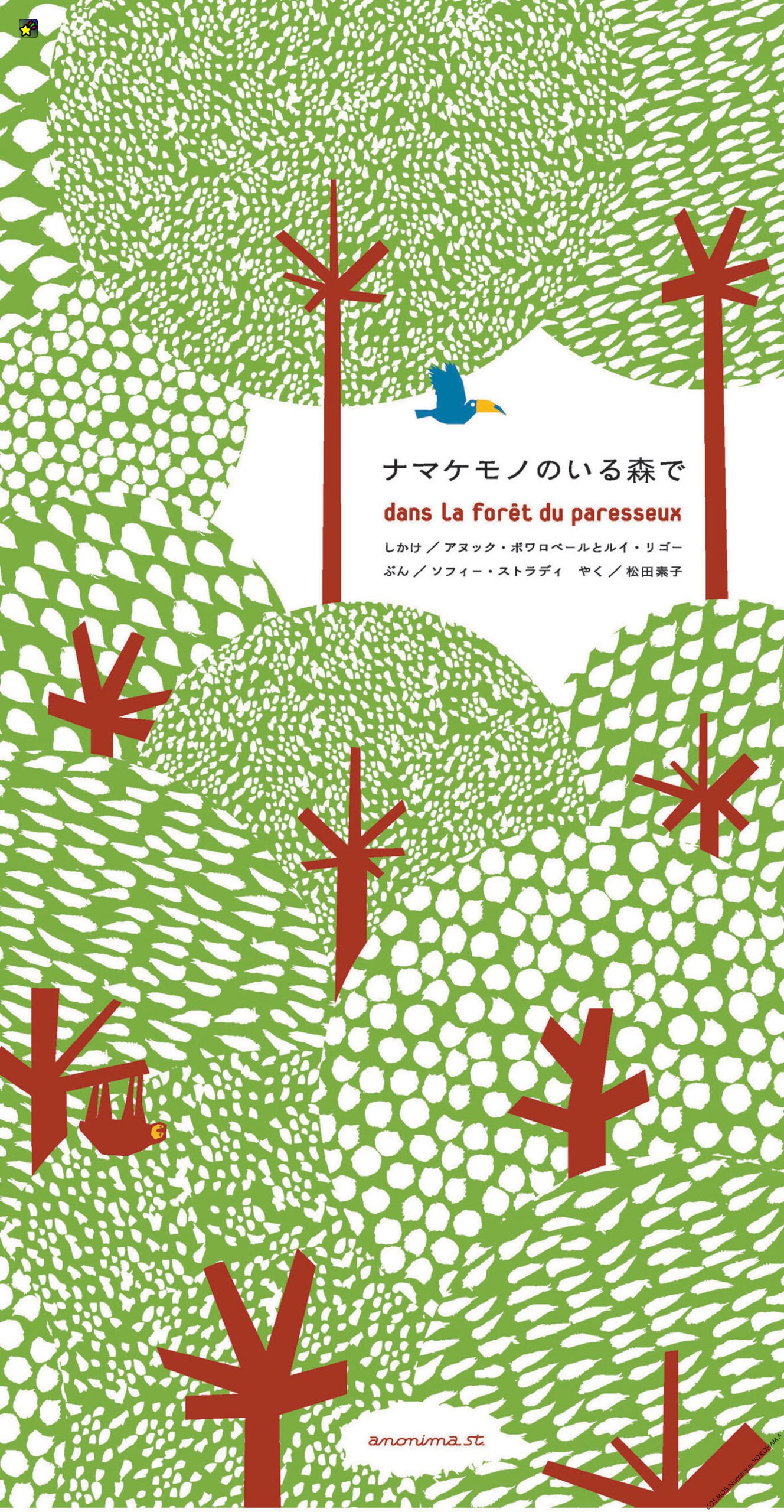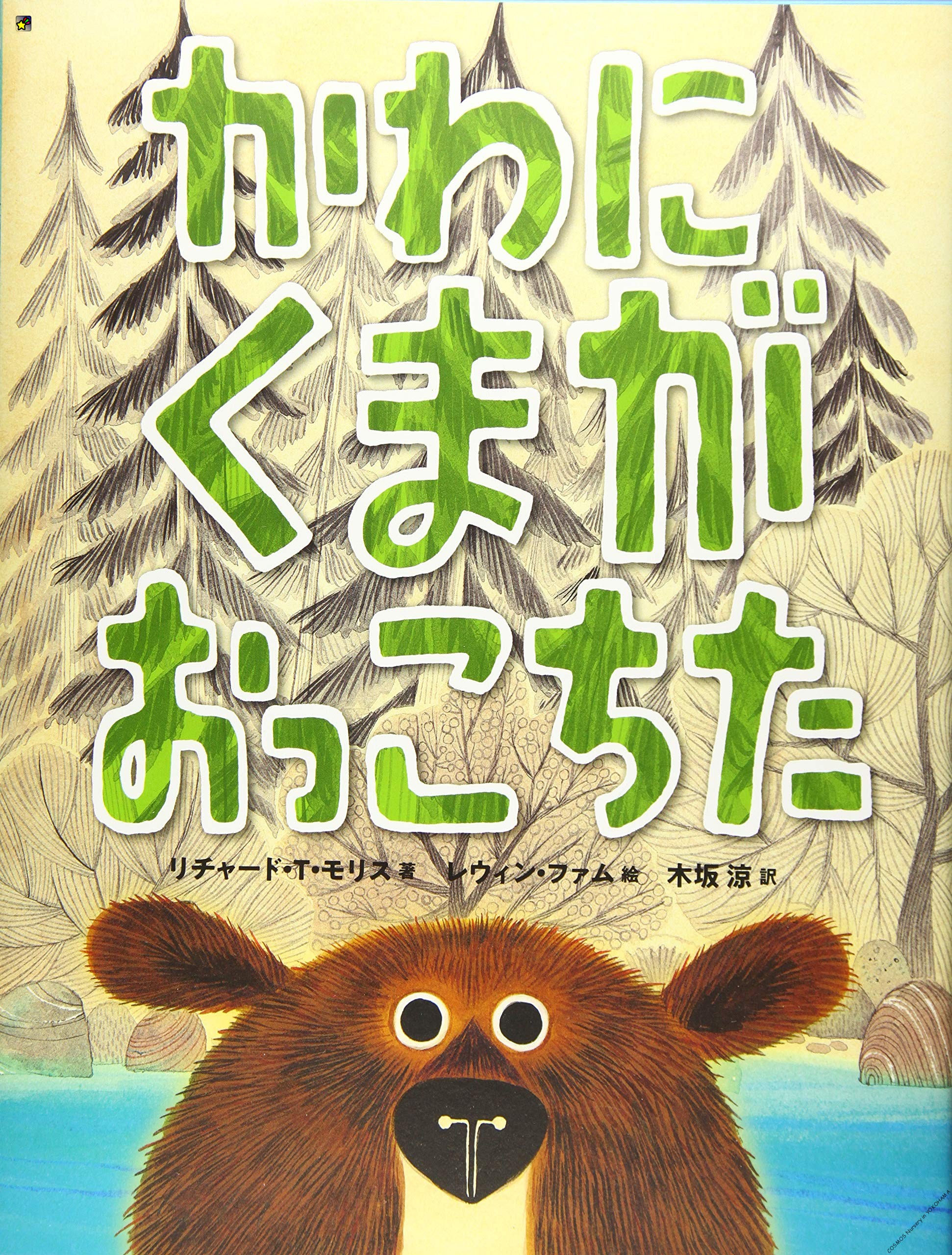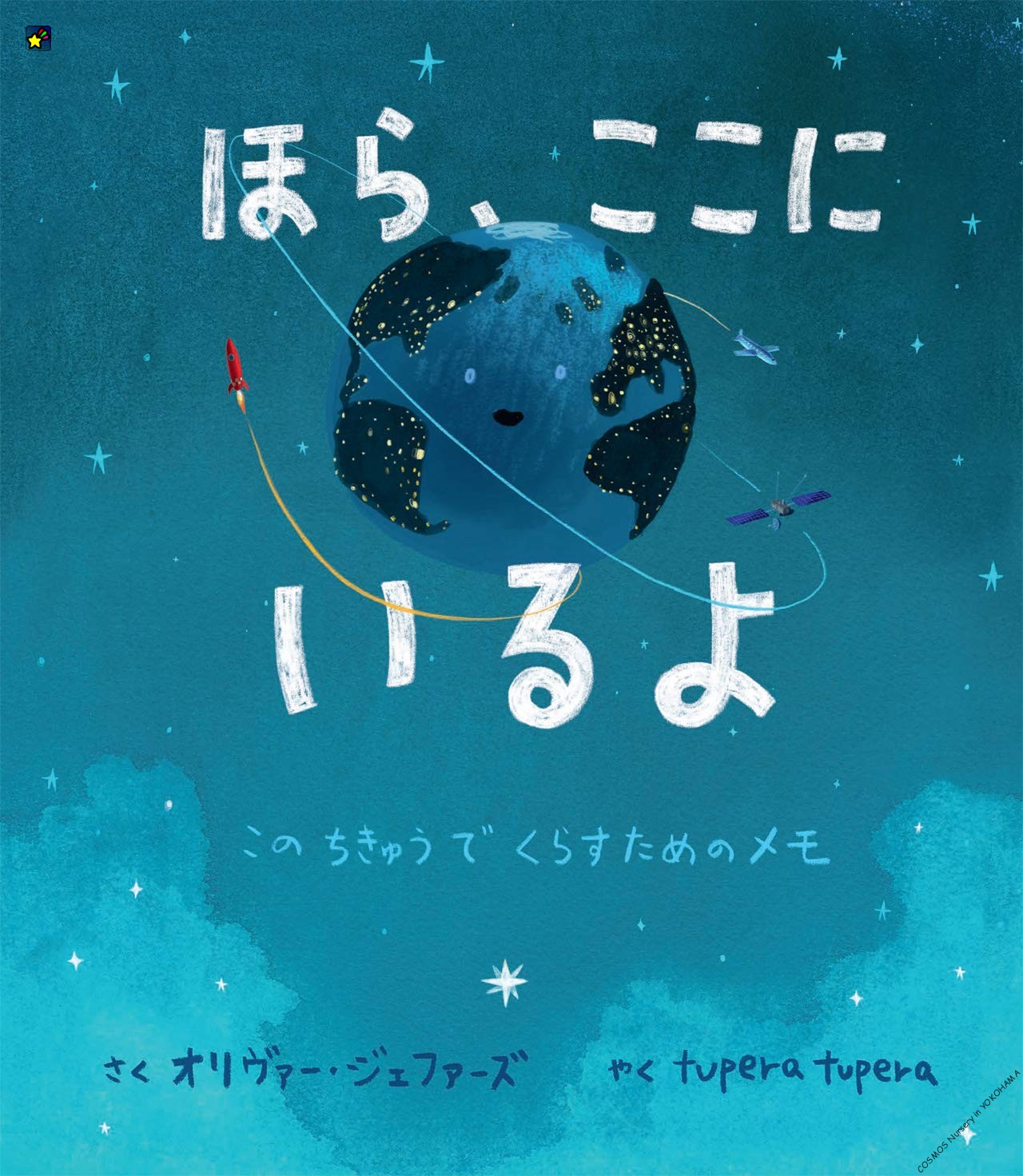世間で言われる“自己責任”という嫌ぁ~な言葉があります。この言葉は「尻拭いは自分でしなさい。わたしたちは責任を負わない」という排除の意味で使われがちです。これは、“自業自得”と同義として使われています。しかし、少なくとも人権の文脈で捉えるのであれば、本来の意味は「自分のことは自分で決める」という本人の自由意志・自己決定についての言葉です。英語ではResponsibilityと言いますが、Response=応答というのは「神の呼びかけ(Call)に応答する(つまり、Call & Response)」ということが本義です。
「神の言うことだから無批判に受け入れるべき」と思われがちですが、それは盲信であって相互のやり取りである応答ではありません(本義としてもそのような意味として使われていません) 人はロボットではないので、他者からの呼びかけをどう受け止めるのか、他者からの呼びかけにどう応えるのか、という行動以前の意志がResponsibilitiyの本質となります。そのため、“自己責任”を行使する時には家族・友人・同僚・専門家から意見を募り、または彼らからの一方的で痛烈な批判を甘んじて受けながら、物事を自ら選び取るのです。
では、わたしたちに自分で決める自由があるとして、わたしたちはきちんと選び取れているのでしょうか。「できているかどうか」はとても気になるところだと思います。実は、自己責任とは「正しいものを選び取れたかどうか=勝ち組になったかどうか」という“自業自得”のような結果論ではありません。「“自ら選び取ったことが、自分にどのような結果をもたらしたかを見届ける責任がある”ことを受け入れる」という「心構えを持つこと=応答すること」なのです。そのため、「できているかどうか」を自己責任の評価とはするべきではないでしょう。
結果の良し悪しは自己責任によるものであったかどうかではなく、集団・社会全体として利益(ベネフィット)と不利益(リスク)を正しく見積もれていたかどうかといった評価から考慮・反省・改善するべきものです。そして、その不利益は自己責任の行使者個人に責任を負わすのではなく、集団・社会全体が担うものです。なぜなら、自己責任論が取り挙げられるような状況は、実は社会全体にとって不利益が生じている、また社会がその問題に対応できていないということであり、自己責任論は社会問題を自己責任の行使によるものとして社会の責任を矮小化しているにすぎないからです。自己責任論が叫ばれるようになれば、そこには社会全体にとっての不利益が発生しています。それらは解決すべき社会問題として、福祉・教育・社会制度・インフラの整備をする必要があります。いかに社会全体の不利益を最小化するかが重要なのです。
わたしはこの視点こそ子どもに対する親の子育てのあり方のように思います。子育ては、親が自ら選び取った子どもへの子育ての結末を受け入れ続ける営みでしょう。それは親自身の生き方だけでなく、子の生き方まで担う、非常に長く苦しい自分自身との戦いとなります。だからこそわたしたち保育園は、親・家庭が一人で思い悩まないように、社会として関わり合っていけたら良いなと思っています。
(2023年7月 再掲にあたり加筆修正しました)